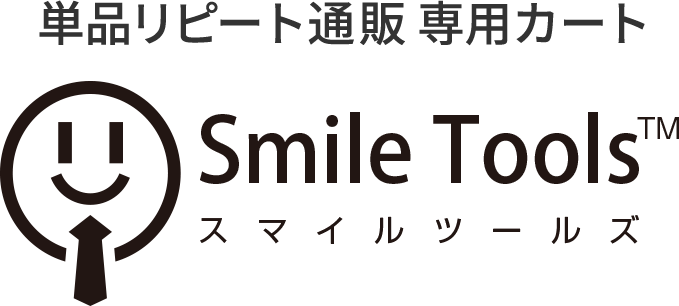ハッシュ化とは?その仕組みと実践ガイド – 顧客データを守りながら広告活用する方法
2025.08.09
オンライン広告の成果を左右する大きな要素のひとつが「自社の顧客データの活用」です。
しかし、メールアドレスや電話番号などの個人情報をそのまま外部と共有することは、情報漏えいや法的リスクを伴います。
そこで注目されているのが「ハッシュ化」という技術です。
この記事では、ハッシュ化の基本概念から広告配信での使い方、安全に運用するためのポイントまでをわかりやすく解説します。
ハッシュ化とは何か?

ハッシュ化とは、特定の計算式(ハッシュ関数)を使って、元データを一方向的に変換し、固定長のランダムな文字列に置き換える方法です。
変換後の文字列から、元の情報を復元することはほぼ不可能で、セキュリティの高いデータ共有が可能になります。
例えば、メールアドレス sample@example.com をSHA-256方式で処理すると、次のような文字列が得られます。
d96f4cbfc0d99cb4f8222c3cbb6939063f6295077e3...このハッシュ値だけでは元のメールアドレスを特定することはできません。
暗号化との違い
暗号化は、特定の「鍵(復号キー)」を使うことで元のデータに戻せます。一方、ハッシュ化は復号ができない一方向処理です。このため、仮にハッシュ化された情報が漏れても、すぐに元データが判明するリスクは低くなります。
広告運用におけるハッシュ化の活用シーン

安全に顧客リストを使う
広告配信では、既存顧客と類似したユーザーをターゲティングするために、メールアドレスや電話番号を使った「顧客リスト広告」が活用されます。
しかし、生のデータをそのまま渡すのは危険です。ハッシュ化すれば、個人情報を伏せたまま、広告プラットフォーム側のデータと突き合わせることができます。
仕組みの一例(カスタマーマッチ型)
- 広告主が自社顧客データをSHA-256でハッシュ化
- ハッシュ値を広告プラットフォームにアップロード
- プラットフォーム側でも同じ方法でユーザーデータを変換
- 一致したユーザーにのみ広告を配信
この仕組みはGoogle 広告だけでなく、Meta広告やAmazon Adsなど主要な広告媒体で広く採用されています。
ハッシュ化の注意点とリスク管理

ハッシュ化は便利ですが、完全な匿名化ではありません。
元データを保持している人がいれば照合可能なため、法律上は「疑似匿名化」に分類される場合があります。そのため、日本の個人情報保護法やEUのGDPRなど、各種法令の適用対象になることがあります。
安全性を確保するためには以下が重要です。
- 元データへのアクセス権限を限定する
- 安全性の高いアルゴリズム(SHA-256推奨)を使用
- ソルト(ランダム値)を追加して推測を困難にする
- 利用目的を明確にし、必要な同意を取得する
- データ保存期間や破棄方法を社内規定に明記する
まとめ:マーケティング効果とセキュリティの両立を
ハッシュ化は、精度の高い広告配信と顧客データの保護を両立できる技術です。
特に既存顧客データを使ったターゲティング広告では、成果を高めながらセキュリティリスクを抑えることが可能です。
ただし、安全に運用するためには技術面だけでなく、ルールや管理体制の整備も欠かせません。
簡単・安全に使える自社開発のハッシュ化ツールをご紹介

当社では、顧客データの安全な取り扱いをサポートするために、自社開発のハッシュ化ツールを提供しております。
こちらのツールは、メールアドレスや電話番号などの個人情報をSHA-256方式で簡単かつ迅速にハッシュ化できる無料のオンラインサービスです。
専門知識がなくても直感的に操作でき、入力したデータを即座に不可逆な文字列に変換します。
また、複数データの一括ハッシュ化にも対応しているため、広告運用やデータ連携における安全性向上に役立ちます。お手元の顧客情報を直接公開せずに活用したい際や、Google 広告のカスタマーマッチ用リスト作成など、幅広い用途でご活用いただけます。
ぜひ以下のリンクより無料でお試しください。安心・安全なデータ活用の第一歩をサポートいたします。
この記事をシェア