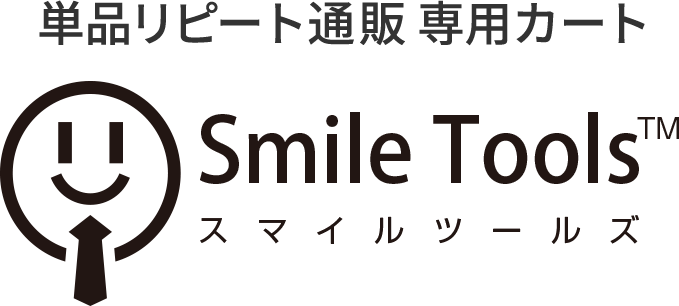2024年景品表示法改正で何が変わった?EC事業者が押さえるべきポイントと実務対応
2025.08.04
2024年10月、景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)が大きく改正されたことをご存じでしょうか?
この改正は、広告表現や景品キャンペーンを展開する全てのEC事業者にとって、非常に重要なものです。違反すれば、金銭的リスクだけでなく、ブランドイメージの毀損にも直結します。
本記事では、改正の背景や具体的な変更点、そしてEC事業者が取るべき実務対応について分かりやすく解説します。
景品表示法とは?まずは基本を確認

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、「商品やサービスの表示に関する誤認を防止し、消費者の利益を守る」ことを目的とした法律です。
特に、不当な表示によって消費者を誤認させたり、過剰な景品類で購買意欲をあおったりする行為を規制するものです。
ECサイトや通販ビジネスでは、LP(ランディングページ)や広告、商品説明文などを通じて商品を紹介する機会が多いため、この法律への理解と対応は不可欠です。
もし景品表示法に違反する表現があった場合、公正取引委員会や消費者庁などから以下のような厳しい措置が取られる可能性があります。
- 措置命令(違反内容の公表と是正命令)
- 課徴金(違反による売上に応じた金銭的制裁)
- 行政指導や改善指示
- ブランド信頼の毀損による顧客離れ
特に2023年の改正以降は、EC事業者への監視がより強化されており、小規模事業者やD2Cブランドでも対象となるケースが増えています。「知らなかった」では済まされないため、まずはこの法律の基本を押さえておくことが重要です。
次章では、景品表示法における「不当表示」の代表的な3パターンと、実際に起こりうる事例を解説していきます。
不当表示の3つのタイプ

景品表示法では、消費者に誤解を与える「不当表示」を大きく3つに分類しています。それぞれの内容と、EC事業者がやってしまいがちな実例を交えてご紹介します。
1. 優良誤認表示
定義:
実際の品質・機能・性能・製造方法などに比べて、著しく優良であると誤認させる表示。
事例:
- 「医師も推薦!」と記載しながら、実際には監修していない
- 「シミが完全に消える」といった医学的根拠のない表現
- 素材に関して「100%天然成分」と強調していたが、実際には一部合成素材を含んでいた
ポイント:
抽象的な表現でも、あたかも科学的根拠があるように見せる場合、違反となる可能性があります。広告表現には第三者の推奨や機能性訴求の裏付け(エビデンス)が求められます。
2. 有利誤認表示
定義:
価格やサービス条件などが、実際よりも著しく有利に見えるような表示。
事例:
- 「通常価格5,000円 → 今だけ1,000円!」と表示していたが、実際には常に1,000円で販売していた
- 「先着100名様限定キャンペーン」としながら、実際には100名を超えても割引を継続していた
- 「送料無料」と表示しながら、特定地域には別途送料がかかっていた
ポイント:
「通常価格」や「期間限定」といった表現を使う際は、その根拠(実際の販売価格や適用期間)をしっかり管理する必要があります。打ち消し表示も目立つ形で提示しなければいけません。
3. その他誤認されやすい表示
定義:
出所や実績、第三者の評価などに関して、誤解を与えるような表示。
事例:
- 「日本製」と記載しているが、実際には海外で製造されたOEM商品だった
- 「モンドセレクション金賞受賞」と記載しながら、実際には過去の別商品が受賞していたものを流用していた
- 「○○協会認定」と表示していたが、その協会自体が企業内の任意団体だった
ポイント:
原産国や認証、受賞歴を表示する際には、誰が認定したのか・いつ取得したのか・どの商品が対象かまで明確にする必要があります。曖昧な権威付けはトラブルの元です。
これらの表示違反は、故意でなくても「結果的に誤認を与えてしまった」と判断されれば処罰の対象となります。とくにD2Cや単品通販など、誇張しがちなマーケティング表現には細心の注意が必要です。
景品類の制限
- 懸賞景品:クイズ・抽選などに参加させて与える景品(上限あり)
- 総付景品:購入や来店によって必ずもらえる景品(取引金額に応じて金額制限あり)
特に「送料無料」「今だけ価格」「最大80%OFF」などの表現には注意が必要で、明確な条件や打ち消し表示を併記しなければなりません。
2024年10月の改正で何が変わった?

今回の改正は、より実効性の高い法律として、違反への対応を強化するものです。
1. 直罰規定の導入
従来は行政による措置命令を経た後に課徴金が科されていましたが、今後は違反が確認されれば即座に罰金(100万円以下)を科すことが可能になります。
これにより、意図的・悪質な表示を排除しやすくなります。
2. 第三者にも責任拡大
広告代理店やインフルエンサーなど、表示の「関与者」にも罰則が適用されるようになります。
たとえば、PR記事で根拠のない美容効果を記載した場合、企業だけでなく投稿者側にも責任が問われます。
ECサイトがPR・UGC施策(User Generated Content = 口コミ・ブログ記事などのユーザー生成コンテンツ)を行う際も、事前の台本確認や表示ルールの共有が不可欠です。
3. 課徴金制度の強化(再違反企業には最大4.5%)
景表法違反が再発した場合、売上の4.5%(通常の3倍)の課徴金が科される制度も新たに導入されます。対象は、過去10年以内に措置命令を受けた企業です。
4. 確約手続の創設
自主的に表示の是正と再発防止策を提出し、消費者庁が認めれば、課徴金を免除される「確約制度」が創設されます。
これは、軽微な違反に対して柔軟に対応できるようになる一方、事前のリスク察知・早期対応が求められる時代になるとも言えます。
ECサイトが注意すべき表示の具体例

景表法は決して“他人事”ではありません。とくにD2C・単品通販・定期購入モデルでは、以下のような表示がチェック対象となります。
- 「今だけ」「特別価格」といった表現に、価格の通常比較対象が明記されていない
- 「最安値」「他社比較」の根拠が提示されていない
- 「送料無料」の適用条件が小さく書かれている
- 総付景品キャンペーンの景品金額が上限を超えている
- インフルエンサーの投稿で誇大な体験談が記載されている
こうしたリスクを避けるためにも、表示ルールの定期見直しとコンテンツ監修のフロー整備が急務です。
今すぐできる!EC事業者のための3つの対応策
1. 自社LP・商品ページの表現見直し
- 強調表現と打消し表示のバランス
- 景品額、使用条件、文言の整合性確認
2. パートナー・制作会社との契約確認
- 誰が表示責任を持つか、契約書や指示書で明確に
3. 内部ガイドラインとフローの整備
- 表示レビューの基準化、担当者教育、改正ガイドラインの社内共有
まとめ:景表法改正は「チャンス」としてとらえるべき
今回の改正は確かに規制強化ではありますが、逆に言えば健全なEC運営企業が選ばれる時代の到来とも言えます。
消費者は「誠実な情報提供をしている企業」に信頼を寄せる傾向が高まっています。
正しい表示・透明な訴求によって、中長期的なブランド構築にも繋がるのです。
スマイルツールズなら、広告設計・フォーム設計・分析まで、EC運営に必要な仕組みがワンストップで整います。
「改正に不安がある」「どこを直せばいいかわからない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。施行後の今だからこそ、着実な対応を進めていきましょう。
この記事をシェア